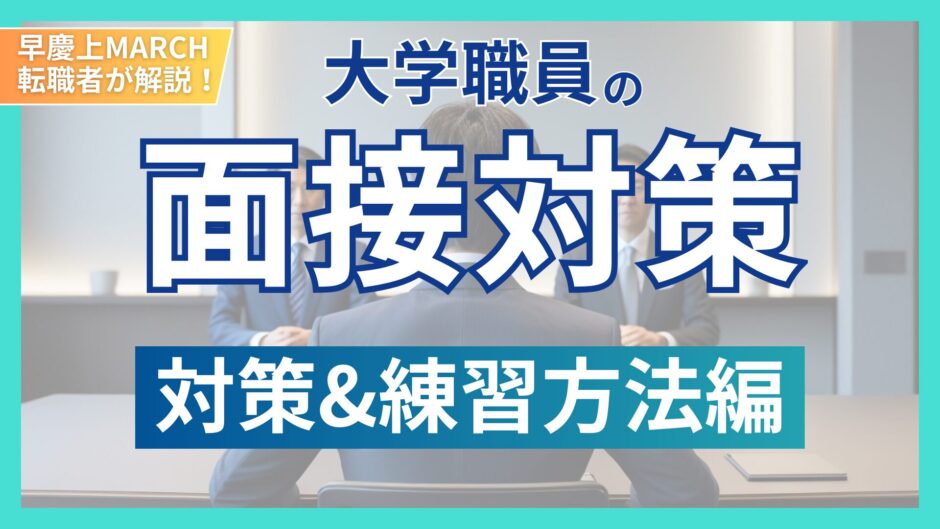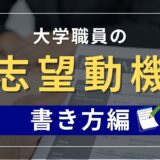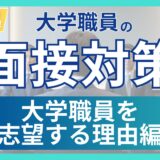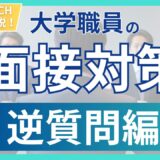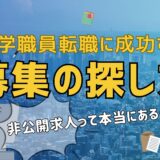「どうしたら面接でうまく話せるようになりますか?」
「効果的な練習法や対策法はありますか?」
大学職員を目指す方をマンツーマンでサポートする中で、このような質問を必ずいただきます。
面接の話し方については、練習方法次第でかなり上達すると考えています。
本記事では、早慶上MARCHで3校内定を獲得し、現在は一次面接官を務めることもある筆者が、面接での話し方のコツや対策方法を解説します!
目次(読みたい場所をクリック!)
想定質問を準備しよう
面接で何が聞かれるか想定できないと、回答の準備や練習もできないため、まずは想定質問を考えましょう。
まずは志望動機・自己PRを中心に
一番最初に想定質問を考える際は、ひとまず志望動機や自己PRなどオーソドックスなものをリストアップしておけば良いでしょう。
「こんなことも聞かれるかも」といった深掘りや更問い系の想定質問は、回答を作っているうちに思いついたりするため、最初にあまり時間をかけて絞り出さなくても良いという考えです。
また、大学職員の中途採用面接では、「自分を物に例えると何ですか?」といった新卒採用時によく聞かれたような、謎に自己分析を試してくるような質問は基本的にされません。
中途採用で面接官が知りたいのは、一言でいえば「あなたはうちで使えるか」です。
それを測るために、スキル・経験・モチベーションなど様々な角度で聞いてくるわけですが、オーソドックスな質問(+深掘り)で終始することが多いです。
- 本学への志望動機を教えてください
- 自己PR(強み)をお話ください
- なぜ大学職員になろうと思ったのですか?
- 本学で成し遂げたいことは何ですか?
- どんな部署で勤務したいですか? 等々
上記のあたり等をまずは優先的に準備していくことをおすすめしますが、私がココナラで出品している「大学職員転職ノウハウまとめ」資料では、実際によく聞かれた質問36選と回答例(NG例含む)も載せていますので、そちらもご参考ください。
回答を準備しよう
台本に書き起こし
志望動機や自己PRはESの段階ですでに書いているかと思いますが、私は面接用にも回答内容をすべて書き起こしていました。
ESと面接では、一文一文の長さや順番なども微妙に異なりますし、書き起こして可視化した方が細かい言い回しや抑揚の調整がしやすいためです。
ポイントだけ覚えておいて、あとはアドリブで勝負という人もいますが、その方法だと、本番で言い方を間違えてしまったり、その帳尻を合わせるために話が少しずつズレてしまったり、という危険があるような気がします。
暗記はしない
ただし、書き起こす目的は「暗記」というよりも、整理と理解のためです。
セリフを暗記して、一言一句同じように面接で話さなければ、という心構えでいると
- 少し言い間違えただけでテンパる
- 回答ボリュームや内容の臨機応変が効かなくなる
という懸念があります。
そのため心構えとしては、「どう聞かれてもスラスラ答えられるよう、頭に映像が浮かぶくらい詳細に理解しておく」というスタンスです。
その意味でも、書き起こすことで、細かい時系列や因果関係などが整理され、理解度や引き出すスピードが大きく向上します。
効果的な伝え方
ESの書き方解説記事の内容と一部重複しますが、相手に効果的に伝えるポイントとして、私は以下のあたりを意識していました。
面接はキャッチボールですので、一答あたりに話す分量は簡潔にしましょう。
ESで書かれている内容と同じ分量を一気に話されても、面接官は覚えきれません。
たとえば「強みを教えてください」と聞かれた際、ESではエピソードも詳細に書いていたとしても、面接では強みだけを端的に答えて、エピソードはさわり部分だけ話すかどうかという分量に収めるのが良いでしょう。
聞かれた質問には、結論を最初に答えましょう。
根拠や補足などは後から付け足せば良いのです。
当たり前のことのように聞こえますが、答えづらい質問などになると結論ファーストで答えられなくなる人が意外と多いです。
全ての回答にそのまま当てはめる必要はありませんが、PREP法を意識すると相手に伝わりやすくなります。
前述の結論ファーストにもつながります。
他にもSTAR法やDESC法など、伝え方のフレームワークはいくつもありますので、回答内容に応じて、もしくは自分に合うものを意識してみましょう。
回答および根拠をとにかく具体的にしましょう。
具体性がない回答は、誰でも言えてしまう内容であったり、説得力が欠けるものになりがちです。
後述する5W1Hなども意識して深掘りしつつ、解像度を上げていきましょう。
- 自身の経験を根拠にする
- 業務シーンを想定する
- 実際の取り組みを挙げる
- 数値で定量的に示す 等々
深掘りの質問を想定
深掘りや更問いの想定質問を本格的に考え始めるのは、この段階です。
回答を考えて書き起こしを進めながら、「自分が面接官ならこんなことも聞いてみたいかも?」というアンテナを立てておき、深掘り質問&回答を並行して考えていきましょう。
また、面接官から更問いがされなかったとしても、自分の回答を深掘りして解像度を上げておくことで、説得力が大幅にあプします。
- 面接官)現職で力を発揮したエピソードを教えてください。
- 自分) ○○の案件で、○○を行うことで、○○のような成果を上げることができました。
- 面接官)その中で課題になったことは何でしたか?
- 自分) ○○をする部分がもっとも課題となり、○○部署の協力を得ることで乗り切りました。
- 面接官)周囲を巻き込むときはどのように行動することを意識していますか?
深掘りするにあたっては、以下の観点を意識することをおすすめします。
- Why:根拠は何か。なぜそう考えたのか(行動したのか)。
- How:どのように。
- When:いつか。どのくらいの長さか。期限はいつか。
- Who:相手の立場は何か。自分の役割や立場は何か。何人規模に対してか。
- Where:どこの場所や規模で(世界/日本/県内)。どこの分野で。
- What:何をするのか(したのか)。
よくある5W1Hのフレームワークですが、特にWhyとHowの観点で深掘りしてブラッシュアップすることが重要です。
面接の練習方法
声出し+イメトレで練習
回答まで準備したら、あとは何十回とひたすら練習あるのみです。
面接においては、内容と同じくらい話し方や印象も重要ですので、隙間時間を上手く使って小まめにやりましょう。
具体的には、【声に出して練習+イメトレ】両方やることをおすすめしています。
声に出すことで抑揚やスピード感などアウトプットに特化した練習ができ、
イメトレは、頭の中でアウトプットしつつ、同時にそれを客観的に分析することができます。
練習を繰り返すことで、言葉の間合いや、細かい言葉選びなどが徐々に洗練され、相手に届きやすい喋りに変わっていきます。
注意するポイント
練習する際は、特に以下を注意しましょう。
- 堅くて不自然な話し方になっていないか
- 初めて聞いた人でも理解できるスピードか
- 一文が長すぎないか
- 間が不自然ではないか
朗読しているような堅い不自然な話し方の人を見かけますが、「面接のために作ってきた話なのか」と嘘っぽく聴こえてしまいます。
ポイントは、友達に説明するくらい自然に喋れるように意識することです。
逆質問の準備
面接の最後には、「何か質問はありますか?」と逆質問が設けられることが多いです。
何を質問すると効果的なのか、別記事で解説していますので、併せてご覧ください。