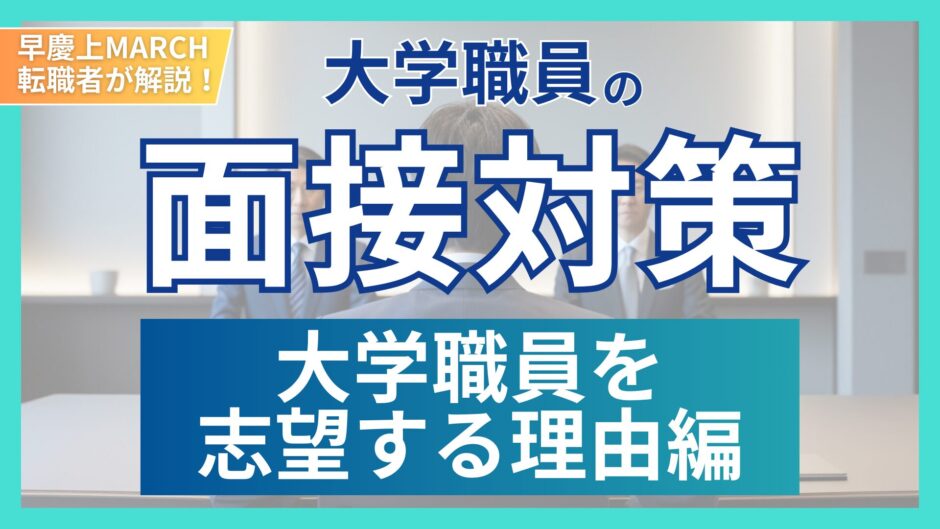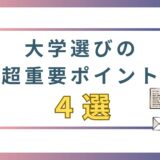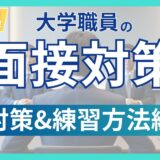大学職員の選考対策で一番苦労するのが、「なぜ大学職員になろうと思ったのか?」という質問への準備です。
どの大学でも必ずと言ってよいほど深掘りされ、落とされる原因にもなりやすい質問だからです。
「仕事が楽なのに高給だから志望している」「高尚な理由なんてないよ」という方に向けて、考え方を徹底的に解説します。
また、多くの方が気付かずにやってしまっているNG例も豊富に紹介しているため、知らずに損をしないためにぜひご覧ください。
目次(読みたい場所をクリック!)
まず押さえるべき考え方
「大学職員を志望する理由」を考えるうえで、以下のポイントを必ず押さえておきましょう。
言われてみれば当然と感じる方も多いと思いますが、他サイトに載っている例文や、私が一次面接官として聞いた回答も、このポイントを踏まえられていないことがかなり多いです。
一見それっぽいが、これらのポイントを踏まえられていないNGな内容例も、次の章で紹介しているため併せてご覧ください。
自身の経験が根拠になっていること
AIが作った回答や、ネットに上がっている回答例は、「あなたでなくても言えてしまう」内容であることが多く、説得力がありません。
大学職員を目指すほとんどの人は「楽なのに給料が高い」などが理由になっており、面接官もそのことを知っているため基本的に疑ってかかってきます。「どこかでパクってきたな」と一瞬で見抜かれます。
そのため、かならず「●●の経験からそう思うようになった」と、ご自身の経験が根拠になった、説得力ある内容になっていることが必須です。
「人生かけて転職したい」と納得できる理由になっていること
「なぜ大学職員になろうと思ったのか?」という質問は「なぜ転職するのか?」とほぼ同じ意図です。
転職というのは人生の中でもかなり大きな選択です。
よほどの思いや理由がなければ踏み出せないのが自然でしょう。業界や業種が変わるとなればなおさらです。
そのため、「たしかにこれは人生かけて転職したいと思えるほどの理由だ」と面接官に納得してもらえる内容になっていなければいけません。
いかにも建前のような浅い理由では、すぐに嘘だと見抜かれて落とされます。
「普通そんな理由で転職しようと思う?」と詰められることもあります。
他の業種ではなく「どうしても大学職員」という理由になっていること
「大学職員でもできるけど他業種でもできる」ような理由ではNGです。
「他業種では叶わず、どうしても大学職員でしか成しえない」ということを論理的に納得してもらえる理由になっている必要があります。
NGな内容
インターン生指導がやりがいになった系
現職でインターン生のトレーナーを担当し、学生が成長していく姿に喜びを感じました。また、キャリア相談にも頻繁に乗り、人の進路をサポートするやりがいを覚えました。そのため今後も幅広く学生をサポートできる大学職員として…
この内容はかなり多くの人が使っており、面接官も聞き飽きているのが正直なところです。
だから絶対落ちるというわけではありませんし、やりがいを少なからず感じたのは事実でしょう。
ただ、この内容で面接官が圧倒的に違和感を覚えることが2つあります。
大学職員の仕事で直接的に学生サポートするものは実は少ないのです。
キャリア相談も職員が直接受けることは稀で、基本的には別で雇っているキャリアカウンセラーがおこないます。
そのため面接官としては、「学生の成長をそばで見たいなら予備校スタッフとか、進路に携わりたいなら人材系企業に行けば?」となってしまいます。
つまり、大学職員でなくてはいけない理由になっておらず、なんならもっと適した職がある、となってしまうのです。
個人の感じ方を否定することはできないため、面接官も「人生変えるほどやりがいになる?」「そんな理由で転職する?」と直接は反論してこないかもしれませんが、心の中では「嘘っぽい」と感じて落とされる可能性は大いにあります。
面接は「反論されなければ勝ち」ではありません。「納得してもらって初めて勝ち」なのです。
地域貢献したい系
現職の業務の中で地域貢献に強く興味を持ちました。大学は教育と研究によって地域と連携し、ともに成長していく拠点だと理解しています。大学職員として地域連携に貢献することで、やりがいを持って…
この内容も面接官としては違和感を覚えます。
たしかに地域連携はいろいろな大学が力を入れていることの一つです。
ただ、大学のメインのミッションはどこまで行っても教育と研究であり、地域連携はいわばサイドメニューなので、「地域貢献したいから大学職員」と言われてもピンとこないのです。
「本当に地域連携がやりたいなら、なぜ県庁や総務省(全国の地方自治体を管轄する官公庁)、もしくは地域活性化をミッションとしている企業に転職しないんだ」ということになります。
大学時代にお世話になった系
大学生時代に学生生活が行き詰まっていた時、学生課の職員の方が的確に相談に乗ってくださったおかげで、前向きにゼミやサークルに打ち込めるようになりました。今の私があるのは、その職員の方の親身なアドバイスや貴学の環境があったからだと感じています。今度は私が同じように学生の未来を支える仕事をしたく…
この方向性は、新卒選考であれば通用しますが、中途採用の選考の場合は「ではなぜ新卒で大学職員にならなかったの?」となってしまいます。
また、この内容だけだと「転職を決意したきっかけ」まで含まれていません。
十中八九そこまで深掘りされますから、どうしてもこの理由を使いたい場合でも、「転職を決意したきっかけ」まで答えられるように準備しておきましょう。
社会への使命感系
少子化が喫緊の課題となっている現代において、国民の知の総和を高めることが重要な政策方針として掲げられています。その中で高等教育を担う大学の役割は非常に重要です。大学自身も改革が迫られているチャレンジングな環境の中、社会への貢献をしたいと考え、大学職員を志望しています。
前半部分は、社会的事象や政府の方針を述べているだけの、いわゆる「誰でも書けてしまう」内容です。
後半では自分の思い(個性)が多少書かれていますが、「様々な国の課題がある中なぜ少子化と教育に注目したのか?」「自分がそこに課題感を持つきっかけは何なのか?」等がまったく見えません。
このように、具体的な経験が根拠になっていないものは説得力が全くありません。
「社会の課題だから」という方向性は、往々にして浅いものになりやすいため、よほど自分の経験・行動と一貫性が示せない限り、あまりオススメしません。
具体的な作り方
ここまでの内容を踏まえて、具体的にどのように作れば良いのか解説していきます。
前提として、最初に解説した「まず押さえるべき考え方」は必ず踏まえるようにしてください。
教育と研究に絡める
オススメの方向性としては、「教育」と「研究」に絡めた内容にすることです。
なぜなら、大学の主なミッションがこの2つであるため、「無理やり感」なく大学に従事したいことをアピールできます。
教育といっても、後輩の育成やインターン生の指導等よりも、できれば学校教育に携わったような経験を語れるとベターです。組織内の育成と、学校教育(大学はこっち)は、毛色が違うためです。
学生時代から教育に興味があり、新卒の就職先も教育関連の企業・組織、という方はアピールしやすいでしょう。
ただ、社会人になってから教育に興味ややりがいを持つようになったということも、経験次第では十分に示すことができます。
たとえば私は、社会人になってから、休日に地域の子どものお世話をしたり勉強を教えるボランティア的なことをしていたため、その経験を根拠に「教育に携わるやりがいを知った」とアピールしました。
そのような経験がない方は、極端な話、今から始めても良いわけです。
オススメなのは、「現職で大学の研究者(教員)と共同で物事を進めた」という経験を根拠にし、「学術研究の力や重要性を感じた」という方向性です。
直接自分が携わっていない案件でも、近くのメンバーや会社として取り組んでいるような案件であれば、使って(多少盛って)も良いでしょう。
複数の要素を組み合わせる
たとえば「教育」と「研究」などの2つの要素を上手く組み合わせた内容にすることで、「他業種ではなく大学」という説得力が出ます。
「教育」だけだと、「大学以外にも一般企業や学校教員などもあるだろう」という反論が出てきますが、「研究」もセットになることで、大学を志望することへの納得感が生まれるのです。
ただし、あまり多くの要素を入れると「大学に合わせて無理やり作った感」が出てしまうため注意です。
なぜこんなに聞かれるのか?
他業界からの転職であれば、「なぜこの業界に入りたいのか?」聞くのは自然です。
ただ、大学職員の面接ではかなりしつこく何度も聞かれます。なぜでしょうか?
それは、「大学職員としてのモチベーションがあるか」を見たいからです。
大学職員になりたい人の多くは、「仕事が少なくて楽」、「ぬるま湯で働ける」といった理由で志望しています。
そのような人が実際に入職すると、主体的に仕事を取りにいくことはおそらく少ないでしょう。
しかし、少子化のなか大学を本気で改革するために、職員一人ひとりのパフォーマンスが重要になっている昨今、本当にモチベーションがある人を採用したいというわけです。
自校だけでなく業界をリードしていく使命のある、早慶上MARCHなどの大学では特によく聞かれます。
また、よく聞かれるだけでなく、落とされる原因になりやすい質問でもあるため、ぜひ十分に対策しましょう。