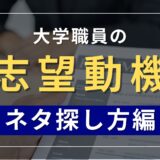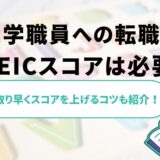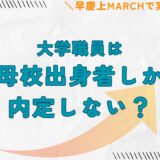「大学職員転職の筆記試験ってどんなものが出るの?」
「面接対策に時間を使いたいから、ウェブテストは勉強しなくても大丈夫?」そんな声が良く聞かれます。
なるべく時間をかけず、でも最低限ここまで対策しておけば概ね大丈夫と言えるであろう、現実的な筆記試験対策を解説していきます!
目次(読みたい場所をクリック!)
大学職員の中途採用選考の筆記試験
大学職員の中途採用選考の筆記試験は主に以下3つです。それぞれ順番に対策方法を解説していきます。
大学によってどの試験が課されるか傾向はあるものの、年によって変わる可能性もあるため、以下の1,2は最低限対策しておきましょう。そうすることで、ほとんどの大学の筆記試験に対応できるようになります。
Webテスト
Webテストが悪いと落ちる?
巷では、「Webテストは悪くても内定できるし、対策してくても良い」という噂もあります。
Webテストの出来が悪ければ普通に落ちます。
大学側はお金を払ってWebテストを実施しているわけですので、成績を全く選考に使わないということはあり得ないためです。
序盤のWebテストで落とされたら、その先に進むチャンスを失うわけですから、全く対策しないというのはオススメできません。
ただ、人事部に聞いた話では、足切りとして使っている大学も多いようです。また、面接に進んだ以降はウェブテストの成績はほぼ考慮されないようです。
そのため、ウェブテスト成績で上位を狙う必要はなく、足切りを突破できるくらいの適度な対策を行うのが現実的でしょう。
ウェブテストはC-GAB(玉手箱)を対策せよ
各大学で課される筆記試験のうち、最も多いのがウェブテストです。ウェブテストもいくつか種類がありますが、大学職員の中途採用選考ではほとんどC-GAB(玉手箱)が使われています。
そのため、C-GAB(玉手箱)の対策をしておけば、ウェブテストはほぼカバーできていると言えるでしょう。
そもそもC-GAB(玉手箱)とは、言語、計数、英語、性格診断の4つの分野で構成されている、総合的な能力を測定するウェブテストの一種です。一般企業の新卒採用時でよくあるSPIとは別のものです。
C-GABと玉手箱の主な違いは受験場所です(C-GAB:テストセンター、玉手箱:ウェブでセルフ受験)
他にも電卓の使用可否、出題範囲など細かい違いはあるものの、問題内容はほぼ同じものと捉えて良いでしょう。
なるべく手間をかけずに通過できる対策方法は?
結論、市販の問題集を1冊買って一通り解きましょう。
もっと時間をかけてしっかりと対策する方法はいくらでもありますが、本業が忙しい中で書類・面接の準備等も必要なことを考えると、この方法が最もシンプルで有効でしょう。
繰り返しますが、ウェブテストは足切り的な側面が強いため、成績上位を狙う必要はないのです。
時間配分を意識する
C-GABも玉手箱も、「時間が足りなくて解き切れなかった」という声を多く聞きます。
実際どちらも時間的にはかなり厳しい問題量なため、解けそうな問題を選別しながらサクサク解き進める必要があります。
私は以下の時間配分を意識していました。自分の得意分野によっても変わってきますが、目安として参考にしてください。
- 計数理解テスト(非言語)
図表の読み取り…… 29問/16分 - 言語理解テスト(言語)
論理的読解…… 32問:8長文×4問/16分 - 英語
論理的読解…… 24問:8長文×3問/8分
- 計数理解テスト(非言語)
四則逆算…… 50問/10分
図表の読み取り…… 29問/15分
表の空欄の推測…… 20問/20分 - 言語理解テスト(言語)
論理的読解…… 32問:8長文×4問/16分
趣旨判定…… 32問:8長文×4問/12分
趣旨把握…… 10問/12分 - 英語
論理的読解…… 24問:8長文×3問/8分
長文読解…… 24問:8長文×3問/8分
論述・小論文試験
大学の中には、テーマに沿って自分の意見を記述させる、論述・小論文試験を課しているところもあります。
対策はシンプルで、大学業界でトレンドになっているキーワードや時事ネタを日頃からチェックし、自分の考えを持っておくのが、地道に見えて最も近道な方法です。
一般企業で社会人経験を積まれている方であれば、論述方法の勉強はそこまで必要ないかと個人的には思います。
しかし、もし文章力に自信がない人は、以下のあたりの王道の論述法を調べて、意識するだけでも分かりやすい文章に近づくと思います。
- PREP法
- DESC法
- 論理ピラミッド 等々…
業界の時事ネタ探し方
オススメの時事ネタ情報収集方法をご紹介します。
文部科学省の資料
日本の高等教育に関わる動きは、まず文部科学省で検討が始まるため、文部科学省が最も知識が付きます。
ただ、審議会のページの奥深くなど見つかりづらいところにあることも多いのが難点。全ての有効な資料を網羅的に探すのは難しいでしょう。
そこで以下2つはチェックしておきましょう。
- 「大学・大学院、専門学校」のページを全体的にチェック
- 「分野別のキーワード」ページの教育カテゴリーにあるキーワードで大学に関連しそうなものをチェック
Between
株式会社進研アドが運営する、大学業界の時事ネタ情報をまとめているサイトです。
文科省の小難しくて複雑な情報も、分かりやすく解説されています。
大学時報
一般社団法人私立大学連盟が運営する、私立大学の取り組み等を解説しているサイトです。
私は以下3つの使い方をしていました。バックナンバーを全てチェックするのは現実的ではないので、号巻や読む箇所を絞って効率的に使いましょう。
- 各号毎のテーマを見て、業界全体のトレンドや課題を把握する。
- 志望先大学が書いている記事があれば、取り組みを把握するために詳しく読む。
- 志望先大学の取り組みテーマに関連する、大学の取り組みを読み、大学間の強み/弱みや課題等を比較する。
③に関しては、論述試験というよりも、志望動機準備や面接対策に使える方法です。
その他特殊系(特に早稲田大学)
特殊系とは主に早稲田大学を意識して挙げました。早稲田大学の中途採用は、以下の内容を組み合わせた独特の筆記試験を設けています。
年によって形式が異なるため、あくまで例として捉えてください。
- 英語による簡単な自己紹介&PR記述(志望動機、成し遂げたいこと、早稲田の魅力、等々テーマは変動)
- インバスケット試験
- 日本語の論述試験(大学業界の時事ネタ系、早稲田について論じるものが多い)
- 内田クレペリン(時間内にひたすら足し算する試験)
インバスケット試験とは?
上記のうち、個別に対策することで成績が変わってくるのはインバスケット試験です。
- 架空のビジネス上の役職や状況を与えられ、時間内に複数の案件を処理するシミュレーションテスト。
- 取り組む順番や時間のかけ方、コミュニケーション方法を評価する。
- 案件をすべて処理することが正解というわけではなく、明確な回答はない。
例題:
あなたは食品卸会社の販売管理部の課長です。以下の案件を処理してください。
①….. 〇〇エリアの売り上げが伸び悩んでおり、今期目標達成のネックになっている。
②….. 部長から社長プレゼン用資料の作成を指示されている。
③….. 部下からチーム内の人間関係で悩んでいるため相談したいと言われている。
例えば上記のような状況が与えられ、10個くらいの案件を1時間以内にどう処理するか回答させるようなものです。
対策方法
インバスケット試験はそもそも普段ほとんど受けることがないため、どう解いたら良いのかイメージが湧きません。
そのため、対策ゼロの人と、少しでも対策した人とで大きく差が開くことが予想されます。制限時間が厳しく、初動でダッシュが必要なため、なおさらです。
そこで、対策といってもインバスケット試験の対策本や問題集を1冊サラッと目を通すだけでも十分です。
どんな問題が出され、どんな回答例があるのか把握することが重要です。また、特に解説部分を読むと勘所がだいぶ掴めます。
早稲田大学の中途採用の筆記試験を受けることになった場合は、ぜひやっておきましょう。
最後に
筆記試験対策は足切り的な側面が強い大学も多いため、書類準備や面接対策に比べると優先順位がどうしても下がります。「出来が悪くても落ちることは無いだろう」と高をくくって対策しない人もいます。
しかし、落ちた場合は希少な求人チャンスが無駄になってしまい、非常にもったいない事になっていまいます。
そのため、なるべく時間と手間をかけないようにしつつ、最低限の対策はしておくようにしましょう。
Webテストは「慣れ」、論述は隙間時間の小まめな情報収集によって効率的に準備できますので、今回の内容をぜひ参考にしてみてください!