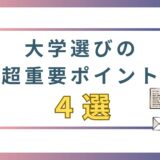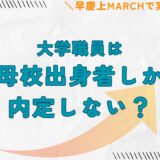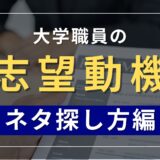「ホワイト高給な大学職員になりたい!」
「これからの日本を担う人材を育成する職業につきたい」
本ブログを読んでくださっている皆さんは、このような思いをお持ちではないでしょうか。
しかし、実は「大学職員」と一口に言っても、大学によって待遇や将来性などピンキリなのです。日本には大学が796校(2024年度 参照:旺文社)あります。
せっかく職員を目指すのであれば、関東圏の方は早慶上MARCHが圧倒的におすすめな理由を、現役職員である筆者が解説します。
本記事は早慶上MARCH以外の大学を否定するものではありません。あくまでも筆者個人が転職において重視する観点において解説したものです。また、一部項目は主に関東圏の私立大学を想定した内容です。
1.給料が高い
大学職員の年収や待遇は、勤務する大学の偏差値と大まかに比例します。
日本では偏差値の高い大学の方が、学生数や受験者の規模が大きい傾向にあり、また研究力も高いことも多いため、収入が多く財務体質が良くなります。
そうなると、人件費として使える予算も多くなるため、職員の給料も高くなるのです。
実際、早慶上MARCHでは40代以降になると、管理職にならなくても年収1000万円を超えることがほとんどです。
国立大学は偏差値が高いところでも、私立と比べて待遇面でかなり差が出てしまうため、注意しましょう。
2.将来の安定性
少子化によって大学業界は斜陽産業になっていますが、早慶上MARCHの将来性については安泰であることが期待できます。
早慶上MARCH等の大学には、100年以上の歴史の中で築き上げてきた社会的ブランド力があります。
各大学とも独自の取り組みで差別化を図ろうとしていますが、社会的ブランド力は十数年そこらで大きく覆るものではありません。
国内子どもの数が減ったとしても、少なくなった子どもたちがトップ校を目指すことは変わらないため、早慶上MARCH等の大学は最後まで生き残るでしょう。
3.転職に有利
早慶上MARCHでの勤務経験は、大学業界内の転職でも、他業界への転職でも有利にはたらきます。
理由の一つは、チャレンジしやすい環境にあるからです。
大学業界は全体的に前例踏襲で、大きな改革には腰が重い文化があります。しかし、早慶上MARCHは日本の将来を左右する人材・研究を生み出す社会的責任があるため、先進的で大きな取り組みに比較的チャレンジしている傾向にあります。
これは事業計画書/報告書、認証評価の資料などを見比べるとよく分かります。
チャレンジングな施策に携われば、そこで得た経験やスキルを転職活動でアピールしやすくなります。
もう一つの理由は、前項でも述べた「ブランド力」です。
早慶上MARCHに在職していたというだけで、「日本トップクラスの大学で物事をリードできる人材」というポジティブな印象を持ってもらえることは多いでしょう。(もちろん内定には具体的なエピソードや根拠が必要ですが)
実際に私の勤めている大学でも、転職していく人がたまに出ますが、転職先は有名大手企業だったり、同じ早慶上MARCHだったりします。
4.面白さがある
繰り返しになりますが、早慶上MARCHは日本の大学の中では改革精神があります。
そのため、働いていても面白さが比較的多い方だと思われます。これは早慶上MARCH以外の知人たちの話を聞いても、実際そのようです。
特に近年はDX推進や国際化など、どの部署にいても新しい取り組みが必要なシーンがあります。
逆にいえば、ルーティーン業務ではない、エネルギーの要る仕事に巻き込まれてしまうというネガティブな見方もありますが、自分の考えを反映して新しいものを形にしていく刺激を味わえるのは事実です。
5.学生も前向きで活発
面白さのもう一つの側面ですが、支援する学生たちが前向きで活発なため、こちらも刺激をもらいながら仕事ができます。
大学間交流や合同研修で、他大学にお邪魔する機会がたびたびありますが、校内で勉強や議論している学生達から伝わってくる雰囲気のようなものは、大学によってけっこう差があるように感じます。
また、学生発でイベントや企画をしたいという相談が主に学生部などに持ち込まれますが、なかなか鋭いチャレンジングな内容が多いように見えます。
とても定性的ですが、働く大学全体の雰囲気にもつながってくるので、意外と大事な要素だと思います。
まとめと補足
以上5つの理由から、職員として働くのであれば早慶上MARCHを強くおすすめします。
ひとつ補足すると、筆者は関東圏在住のため早慶上MARCHを研究して狙っていましたが、関西圏などにある偏差値トップクラスの大学にも同じことが言えるのではないかと思います。
大学職員を目指す皆さんは、大学によって特徴に差があることを念頭に置いて、狙う大学を選んでいきましょう。