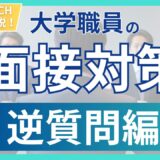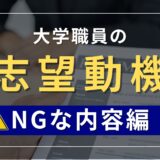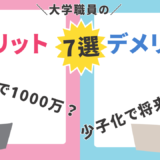私自身や私が面接やサポートをしてきた方々の実際の失敗談をご紹介します。
同じ轍を踏まないよう、最後までチェックしてください!
目次(読みたい場所をクリック!)
私の失敗談①
実施されていない施策を提案できなかった
早慶上MARCH某大学の三次面接でした。相手は、管理職か人事部長と思われる年配の面接官2名。
私はIT企業で営業をしていたため、自己PRの1つで「DXを推進して、教育・研究の質向上に貢献できる」とアピールしました。
すると、「では本学がまだ実施していないIT化施策を提案してください」と質問されました。
「本学でまだ実施していない!?」と心の中で怯みつつ、冷静に用意していたネタを提案しましたが、まだ実施していないのか問われると正直自信がありませんでした。
結局その面接は落ちてしまったため正解は不明ですが、「本学で実施していないか」分からない状態で答えた時点で、私の負けだったと思います。
相手大学が実施している取り組みを全て知るのは現実的には難しいので、やや意地悪にも感じますが、早慶上MARCHではこのようなの質問も飛んできます。
対策(重要)
対策:一次面接の逆質問で「私はこのような施策が有効だと考えているのですが、貴学では現在行なっていますか?」と聞く。
これが最も確実な方法です。
一次面接は若手~中堅の現場職員もしくは人事部担当者が担当することが多く、無難な質問が飛んでくることがほとんどです。
そのため、先ほどのような質問は二次面接以降で聞かれる可能性が高いため、一次面接の逆質問で聞くスタンスでいれば問題ないでしょう。
逆質問の意味
面接の質問には、加点を積極的に狙うべき「攻めの質問」(自己PR、志望動機等)と、減点されないよう無難に終わらせるべき「守りの質問」(現職に不満はないのか等)の、2種類があると考えています。
面接の質問には、「攻めの質問」と「守りの質問」の2種類があります。どちらなのか見極めて回答スタンスを柔軟に変えましょう。
逆質問は「守りの質問」です。私も面接官をやったことがありますが、「逆質問」は純粋に候補者の知りたいことを教えてあげる意図で設けていることが多いです。
「逆質問は熱意を積極的にアピールする場」という説もありますが、ここで大きく加点するケースは私が見る限りあまり多くなく、逆にアピールのためだけに用意してきたような内容をドヤ顔で質問されると印象があまり良くありません。
そのため、逆質問は以下のポイントさえ守っていれば、何を聞いても良いのです。
- 質問の意図が伝わる内容にする。(もしくは伝える)
- 面接官でも明らかに知らないこと・困ることは聞かない。
- 「質問はありません」というのはナシ。(本学に興味がないと思われてしまう)
「改善提案の妥当性」や「自分が考える大学の課題感の認識」を聞いておければ、次以降の面接で「職員の生の声」として根拠・材料に使っていくことができます。
私の失敗談②
現職の紙袋を持って面接に行った
転職活動開始当時、早慶上MARCH以外の大学を1つ受けました。そこの最終面接が、なんと10分も経たずに終了しました。
回答が刺さった感触はなかったため、「何か悪いこと言ったかな」とすぐに思いました。案の定、落選の連絡が来ました。
現在の大学に入職した後、知り合いの伝手で落ちた理由を聞くことがでました。それは「面接時に他企業の紙袋を持っていたから」というものでした。
たしかにその時、営業の合間でしか面接日程が組めなかったため、お客さんに渡すパンフレットを会社の紙袋で運んでいたのです。待合室もなかったことから、面接室に紙袋も持って入りました。
今思えばおそらく「仕事の合間で来るなんて、本気度が足りず失礼」と思われたのでしょうが、当時の私は気に留められていませんでした。
面接内容以外のところで落ちることがないよう、ぜひお気を付けください。
仕事の合間に面接に来ていることが伝わらないようにしましょう。
面接したり転職サポートした方の失敗談
これまで面接官をしたり転職サポートする中で見てきた失敗談です。
相手の頭にほとんど残っていない(流暢な人ほど注意)
一次面接の面接官として駆り出されることや、ココナラでのマンツーマンサポートで模擬面接をする機会が多々あり、面接官側の感覚が分かってきました。
そこでよく見るのが、一見話し上手で流暢に回答している人ほど、言葉数が多かったりスピードが速くて、面接官の頭にはあまり情報が残らないという事態です。
面接官が事前にESをしっかり読み込んでから面接に臨むことは稀なため、面接で聞かされるエピソードは実質ほぼ初耳です。しかも背景知識もない他業界の仕事の話をブァーッと浴びせられるとなっては、頭に残る情報はわずかです。
「ここもう一度話して」と聞き返してくれるならまだ良いですが、聞き返すためのフックになる情報すら頭に残らないと、なにも深掘りされずに終了ということになりかねません。
面接では緊張して早口になりがちなため、話すスピードを半分に落とすくらいの感覚で良いでしょう。また、無駄な言葉・情報を極限まで削ぎ落し、自然な話し方ができるようになるまで、アウトプット練習を繰り返しましょう。
自分が流暢に話せる方だと思っている人ほど、話が長く・速くなりがちなため注意です。
話すスピードは自分が思う半分くらいOK。無駄な言葉を極限まで削ぎ落しましょう。
質問とずれた回答をしてしまう
「困難だったことは?」と聞かれているのに、思わず「困難を乗り越えるための工夫や取り組み」を話してしまっているような、ずれた回答もたまに見かけます。
おそらく一所懸命に回答内容を暗記して練習したことで、柔軟な対応ができなくなってしまったのだと思われます。
自然な回答ができるように面接練習を重ねることは重要です。
しかし、セリフを一言一句暗記するというよりは、ストーリーを理解し、映像が鮮明に浮かぶくらい頭に染み込ませておく、という感覚の方が良いと思います。
その方が緊張した場面でも、面接官の質問に対して、適切な部分を柔軟に切り取ったり加工してアウトプットしやすくなります。
面接練習のインプットはセリフ暗記ではなくストーリー理解。アウトプット練習も重要!
自己PR・志望動機のミス
自己PR・志望動機は、いくつか踏んではいけない注意ポイントがあります。
詳しくは今後別記事で解説しますが、列挙すると以下の通りです。
特に1,2点目をやってしまっている方は非常に多いです。
- 他者との差別化、優位性が意識されていない自己PRになっている
- 志望先大学を褒めるだけ、共感するだけの志望動機になっている
- 主張や根拠に具体性がない
- 「教職協働」や大学職員の役割を勘違いしている
- 学生支援が志望動機になっている
失敗しないために
私や先人達の失敗を、反面教師としてご自身の転職活動に活かしていただければと思い、今回の記事を書きました。
面接の受け答えや書類内容は、自分だけでは落ち度に気付くことがなかなかできません。
ぜひ一度身近な人に見せてフィードバックをもらうようにしましょう。もちろん筆者でもかまいません。